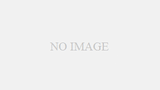はじめに
令和8年度税制改正大綱案と原点としてのタワマン訴訟①の続きですが、このタワマン訴訟、そして、今回の税制改正大綱案について、租税法律主義の観点から考えてみます。実務的に役立つ論点は入っていませんので、興味のない方は飛ばしてくださいね(笑)。
総則6項という“剣”:GAARっぽさが生む不安
タワマン判決の世界で中心的な問題になったのが、財産評価基本通達6項(総則6項)というものでした。
先に結論を言うと、総則6項は運用次第で包括的な否認規定(GAAR)ぽく見える。だからこそ国は、後追いで剣を振るうのではなく、先に数値ルール(壁)を置く方向に動き始めた――私はそう捉えています。
総則6項をごく簡単に言うと、
• 基本はみんなと同じルール(路線価等)で評価する
• ただし、そのルールの結果をそのまま使うのが著しく不適当な場合には、例外として“時価”ベースの評価が出てくることがある
いわば、ルールブックの最後に、「このルールではどうしても不都合が出るなら、例外でレッドカードも出せます」と書いてあるようなもの。
実務家は、これを「伝家の宝刀」「剣」と呼びます。剣は強い。でも、使い方が難しい。
• どこからが「やり過ぎ」なのか
• 何が「合理的理由」になるのか
• 最後は「その人だけ例外扱い」になっていないか(平等)
ここまで来ると、結局、争いは“主観”に寄っていきます。「節税目的が強い」「経済合理性が薄い」など、言葉は客観っぽいのに、実際は評価が割れるからです。
さて、世界的には、「不当な租税回避っぽい取引はまとめて否認できる」という包括的な規定(GAAR)を置く国も多いです。
でも、日本はこの手の“大きな網”を、制度としては慎重に扱ってきました。理由はシンプルで、租税法律主義(特に明確性=予測可能性)へのこだわりが強いからです。だから日本が好むのは、むしろ個別的否認規定(SAAR)。特定の抜け道を狙い撃ちして塞ぐ、というものです。
そんな中で、先ほどの総則6項は運用次第でGAAR的に使えます。だからこそ、タワマン判決で最高裁は、総則6項を「いつでも使っていい剣」にはしなかった。(=例外を認めつつも、適用のハードルを高くした。)
では、最高裁は「その剣を、どうやって縛るべき」と考えたのでしょうか。
宇賀克也裁判官と自己拘束性の法理:例外なら説明せよ
この最高裁の判決には、行政法の専門家である宇賀克也(うが かつや)裁判官が加わっています。彼の専門である行政法の重要な考え方の一つに、「自己拘束性の法理」というものがあります。これはごく簡単に言うと、
国が一度「こうします」と約束したルールは、国自身も勝手に破ってはいけない。
行政は、自分で決めたルールに縛られるべきだ。
というもの。私は、宇賀克也裁判官はまさにこの系譜に立つ人だ、と理解しています。
彼の「裁量を野放しにしない」感覚は、別の事件でもはっきり見えます。たとえば、最判令和6年5月7日(青色申告承認取消し)で、宇賀裁判官は、「不利益処分なら原則として事前に根拠法条と事実を示し、意見を言う機会を保障すべきだ」という強い反対意見を述べています。
この感覚を租税の世界に移すと、こうなります。
ルール(通達)に従った納税者を、あとから“例外”で叩くなら、なぜ例外なのかを、筋の通った言葉で説明できないといけない
つまり、「剣を振るうなら、その理由を説明できなければならない」という発想です。そして、この「説明できるか」という軸は、次の“デュープロセス”の話につながります。
デュープロセス:人はそれを「納得」と呼ぶ
これは憲法31条のデュープロセス(適正手続)の問題でもあります。
憲法31条は本来、刑事手続の規定です。ただ最高裁は、少なくとも「行政の世界でも、処分の性質に応じて適正手続が問題になり得る」という枠組みを前提に議論してきました(いわゆる成田新法事件判決の射程がよく参照されます)。
ただし、ここも大事なので一言だけ。
最高裁は「行政なら何でも事前聴聞が必要」とまでは言わず、権利制限の程度や公益などを総合して判断する、という立場も取っています。
そのうえで、租税の世界でこの“デュープロセスの体温”を測る、現実的な物差しの一つが――
理由の提示(理由付記)がどれだけ具体的か
です。
税務の更正処分などでは、理由付記の制度趣旨が繰り返し整理されており、国税庁の研究論文でも、理由提示が求められる範囲が拡大してきた流れが整理されています。
だから私は、「デュープロセス」という考え方は、最終的にはこう言い換えるのが一番わかりやすいと思います。
1円を取るなら、「なぜ取るのか」を言葉で説明できなければならない。
それが、手続的正当性の最低ラインです。そして――ここが次の章の入口になりますが、「剣で例外を出す」よりも、最初から説明できる形で線を引くほうがいい。
そして令和8年度改正へ:「剣」から「壁(数値ルール)」へ
今回の改正大綱案の象徴が、いわゆる数値ルールです。趣旨としてはこうです。
原則:通常の取引価額相当で評価(5年以内取得・新築の一定の貸付用不動産)
ただし:課税上の弊害がない限り、取得価額ベースで算定した額の80%でもよい(「できる」)
• 相続開始前5年以内に取得・新築した一定の貸付用不動産について、
取得価額を基にした“通常の取引価額相当”で評価する方向
• そのうえで、条件付きで「80%」という目安(下限・フロアの発想)が出てくる
• さらに賃貸割合の扱いも含めて、調整が入る
これは先ほどから言っているように、
• 「総則6項(例外運用)で何でも切れる」=剣
から
• 「あらかじめ線を引いて、仕組みで塞ぐ」=壁(ルール)
へ移っていく動き
まさに、GAARっぽい運用を、SAARの形(具体ルール)へ置き換えたもの、そう理解することもできると思います。これを日常的な感覚で言うと、
• 納得できないケース:
「なぜか分からないけど、あとから国にダメだと言われた」
• 納得できる(はずの)ケース:
「事前にルールがハッキリ決まっていて、その通りに手続きが進んだ」
今回の改正で、「あとから突然怒られる」という不安は減りました。これは一つの進歩とも言えると思います。でも当然、壁には壁の問題があります。
結び:私たちは次に、どこで戦うのか
過剰な租税回避スキームが制度として是正されること自体は、実体的な公平の観点から評価したいと私は思います。税の信頼が崩れれば、最後に損をするのは国民自身に他ならないのですから。
しかし、最後にお伝えしたい懸念があります。
ルールが「数字」だけで決まるようになると、「個別の事情」が無視されてしまうおそれがある。たとえば――
• 「孫のために、どうしてもこの家を買ってあげたかった」
• 「節税のためじゃなく、家族の将来のために投資した」
こうした「一人ひとりの想い」があったとしても、「5年以内」という線一本で、すべてが切り捨てられてしまうかもしれません。
線を引く。その線のたった1日内側と1日外側で、結果が変わる。それは制度設計として仕方ない面もあります。でも同時に、私たちは問い続けないといけない。
• その線引きは、どんな公平を守るためなのか
• 例外がないことが、かえって不公平を生まないか
• 説明できる制度になっているか
少なくとも、この分野においては、総則6項という「剣」と戦う時代の次は、精緻に組み上げられた「制度の壁(数値ルール)」そのものと向き合う時代になるのでしょう。
この「数値による支配」は、法治主義の進歩であることは否定できません。ただ、、、その壁が個人を押しつぶすものでないことを願わずにはいられません。
※具体的な税額計算・申告は税理士業務です。当事務所は相続全体の設計と手続を支援し、税務は税理士と連携します。